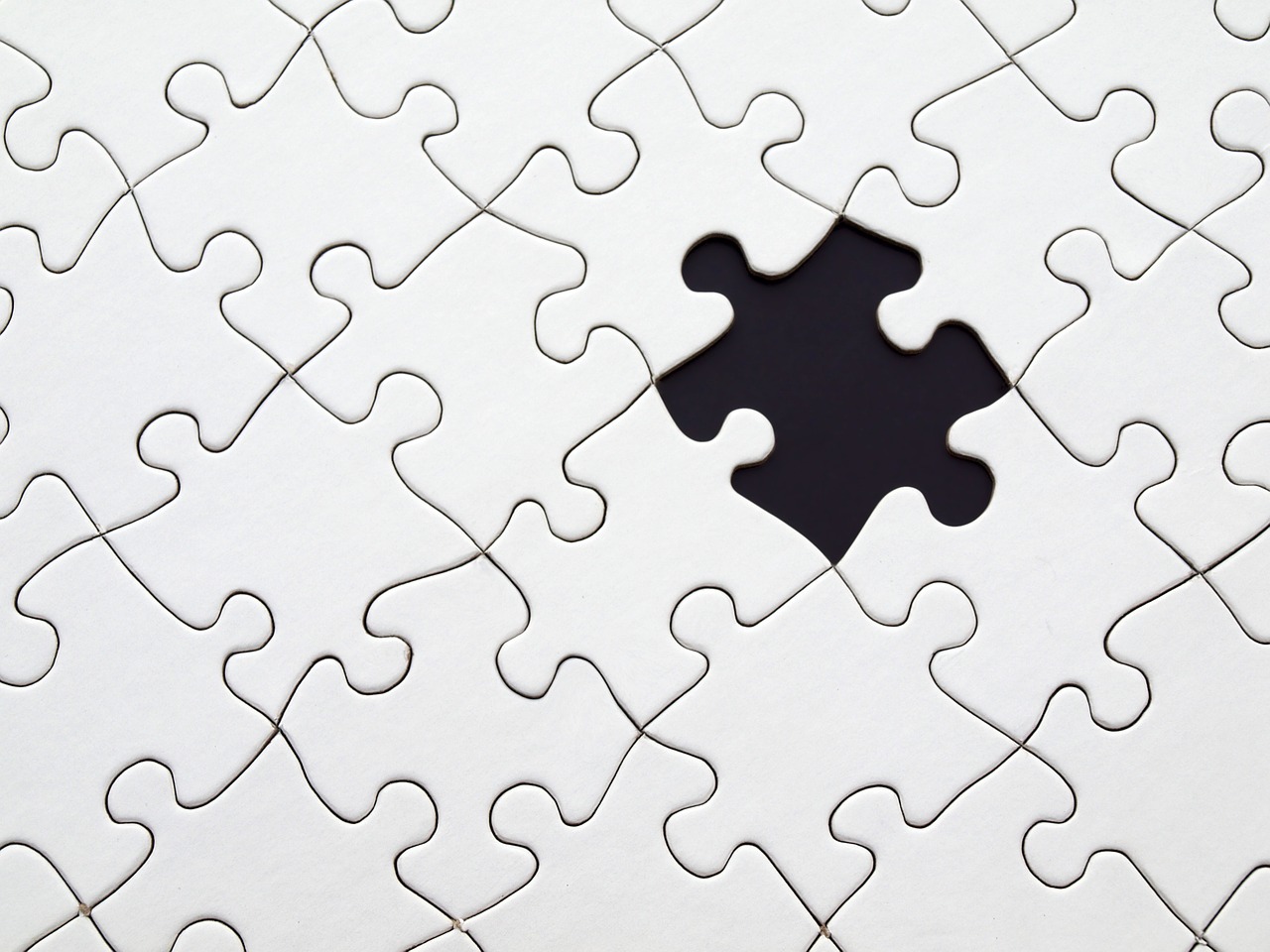相続人の中には、この人だけには遺産を渡したくないと思うような人がいる場合、どのような手段を取ればいいのか、ご存じでしょうか?
もし推定相続人のなかに相続させたくない人がいる場合は、相続廃除という方法で指定した人を相続人から外すことができ、財産を渡さないようにすることができます。
また相続廃除は、よく似た制度としてある相続欠格と混同されがちですが、この2つには大きな違いがあります。
今回は遺産を渡したくない推定相続人がいるという方が知っておくべき、相続廃除に関する基礎知識や相続欠落との違いについてお伝えします。
相続廃除を行うことで、必ず指定した人を相続人から外すことができるとは限りませんので、その要件や手続き方法、申請方法などについてよく覚えておきましょう。
1. 相続廃除とは
相続廃除とは、推定相続人から相続資格を奪うための方法のひとつで、被相続人の意思によって行われます。
被相続人が相続廃除の申し立てをし、それが家庭裁判所に認められると、その推定相続人は被相続人の死後、遺産を相続することができなくなります。
1-1. 推定相続人とは
推定相続人とは、現状のままで被相続人が死亡し、相続が開始された場合に、直ちに相続人となるべき立場の者のことをいいます。
たとえ子どもや配偶者であっても、相続廃除や相続欠格で相続権を奪われたり、被相続人よりも先に死亡したりする可能性があります。
被相続人が生存している時点では相続人になるとは限らないことから、推定という呼び方がされているのです。
1-2. 相続欠格との違い
推定相続人から相続権を奪うもうひとつの方法として、相続欠格がありますが、相続廃除では被相続人の意思にもとづく手続きが必要なのに対し、相続欠格では欠格事由に該当した時点で、法律上当然に相続権がはく奪されます
▼相続欠格について詳しくは以下の記事をご参考ください。
【絶対に相続させたくない時にとるべき相続欠格の制度】
2. 相続廃除の事由となる場合
民法892条には相続廃除が行われる要件として、以下の内容が記されています。
民法第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
つまり被相続人に対して直接的な危害を加えたり、浪費、遊興、犯罪行為、不貞行為などを日常的に繰り返したりしていると、家庭裁判所に廃除事由があると認められやすくなるということです。
3. 相続廃除の事由とならない場合
以下のようなケースでは、高い確率で相続廃除の事由としては認められません。
・推定相続人が被相続人の冷遇や非道な行いに我慢しきれず暴行を加えた
・推定相続人が被相続人の意に沿わない職業選択や結婚を行った
・相続廃除の事由があると判断できるほどの十分な証拠資料がなかった
ただしどのようなケースであっても、相続廃除が認められるかどうかは家庭裁判所の審議に委ねられることになります。
4. 相続廃除を行う方法
相続廃除には、生前廃除と遺言廃除という2通りの方法があります。
4-1. 生前廃除
被相続人が生存中に、自ら推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求する方法です。
生前廃除では被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に廃除の請求をします。
4-2. 遺言廃除
被相続人の死後、遺言にもとづいて行う相続廃除です。
遺言廃除の場合は遺言で指定された遺言執行者が、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所に廃除の請求をします。
5. 相続廃除の申請の流れ
推定相続人の相続廃除を実現するためには、推定相続人廃除申立と推定相続人廃除届の2つの手続きをする必要があります。
5-1. 推定相続人廃除申立
生前廃除の場合は被相続人、遺言廃除の場合は遺言執行者が家庭裁判所に推定相続人廃除申立書を提出して申し立てします。
必要書類
推定相続人廃除申立書の他に下記の書類が必要となります。
・申立人及び廃除対象の推定相続人の戸籍謄本
・被相続人の除籍謄本(遺言廃除の場合)
・遺言書の写し(遺言廃除の場合)
費用
収入印紙代800円がかかります。
5-2. 推定相続人廃除届
推定相続人廃除申立が認められると、調停成立の場合は調停調書が、審判確定の場合は審判書の謄本が家庭裁判所からもらえるので、それを持って10日以内に届出人の所在地もしくは相続人の本籍地の市町村役場へ行き、推定相続人廃除届の手続きをします。
必要書類
・推定相続人廃除届
・家庭裁判所の調停調書(調停成立の場合)
・家庭裁判所の審判書の謄本(審判確定の場合)
・印鑑
費用
費用は無料です。
5-3. 相続廃除はほとんどが認められない!?
ここまで相続廃除についてご説明してきましたが、実は相続廃除が家庭裁判所に認められる可能性はかなり低いといわれています。