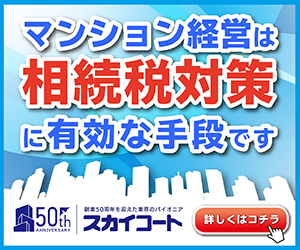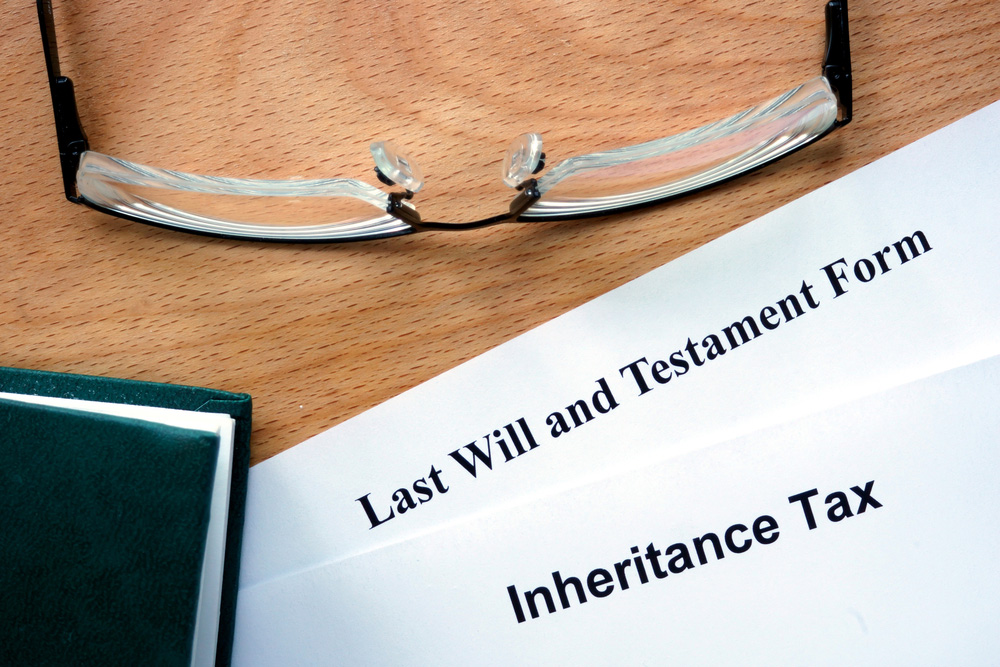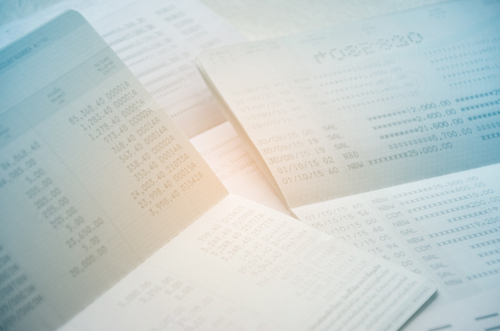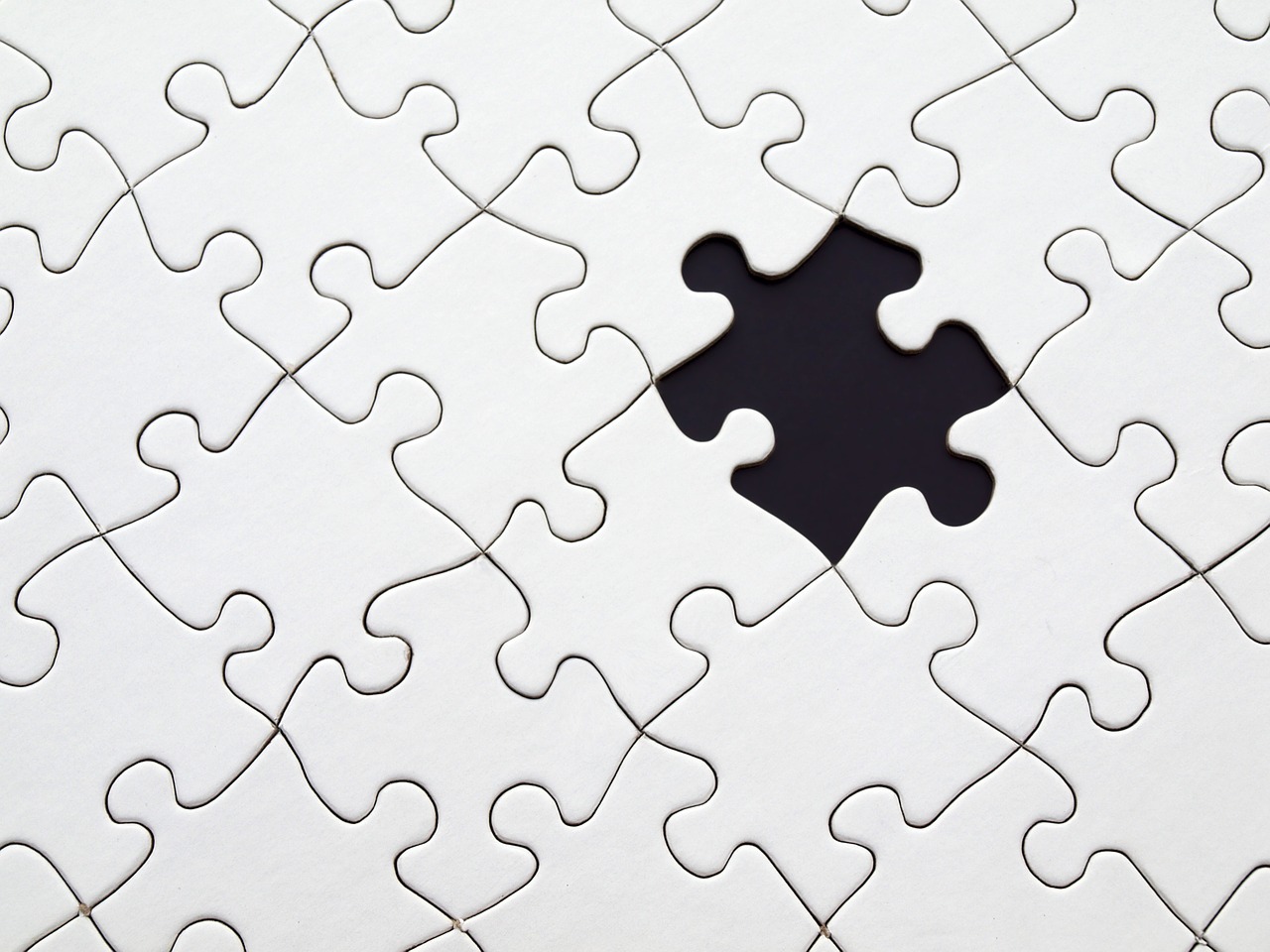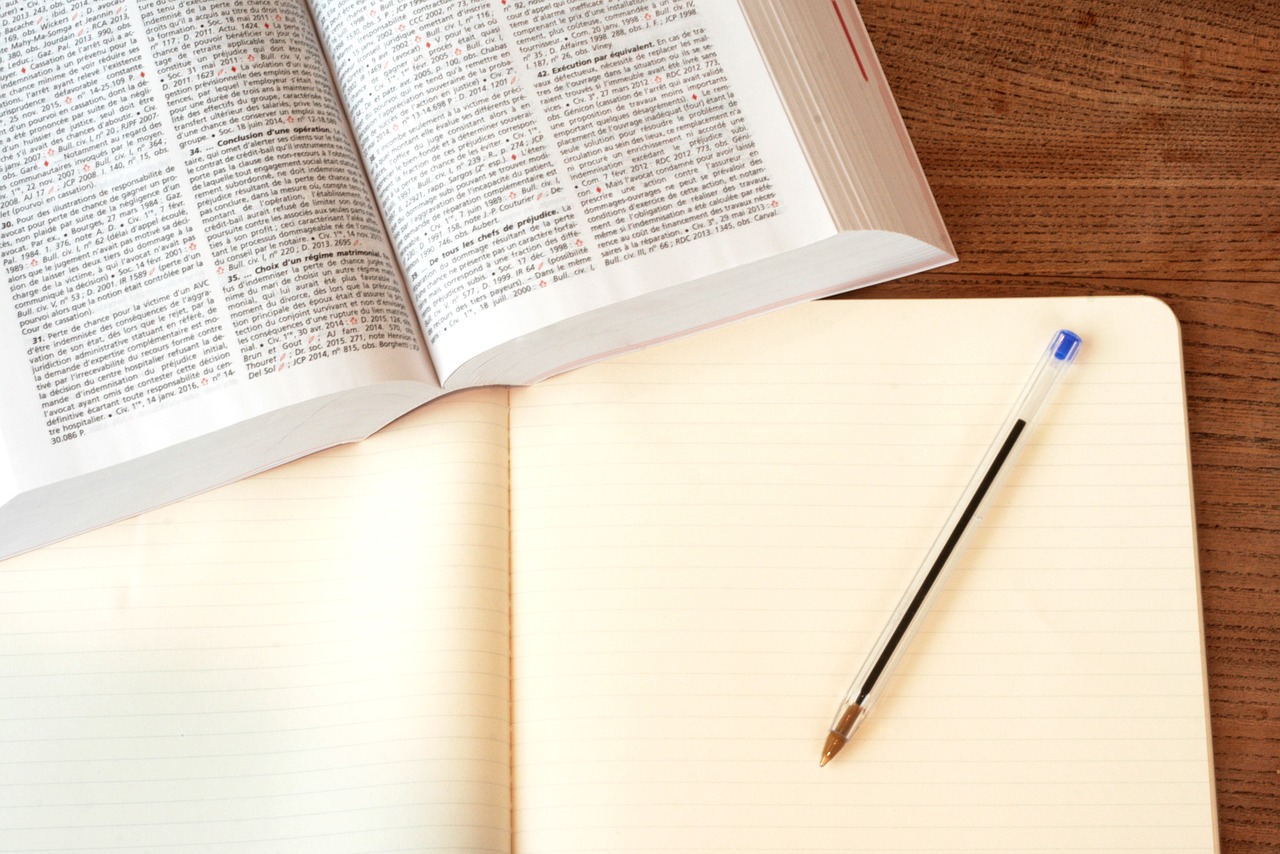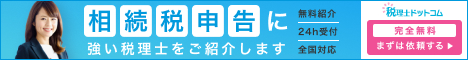【計算例】
1月1日から12月31日までに祖父から20歳以上の孫へ500万円の贈与を行う場合
この場合、特例税率が適用されます。
贈与額500万円 - 基礎控除額110万円 = 課税対象額390万円
課税対象額390万円 × 特別税率15% - 控除額10万円 = 贈与税48.5万円
となります。
また一般税率と特例税率の両方での計算が必要な場合は、それぞれに応じた税額を算出し、合計した金額が贈与税額となります。
1-3.贈与税の申告
贈与税の確定申告の時期は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日、納付期限は3月15日です。
納付は金銭一括で行うことが基本ですが、延納が認められる場合もあります。
基本的に贈与を受けた金額が基礎控除以内の場合は、贈与税の申告は不要ですが、後述する特例を適用するためには、贈与税の申告が必要となるため、注意が必要です。
2.暦年課税の基礎控除を利用して相続税対策を行う
相続が発生すると、死亡した被相続人が持っていた財産は、相続人などに移転されることになりますが、その時に相続税が課税されます。
相続税の負担を軽くするための相続税対策にはさまざまな方法がありますが、生前贈与を行うことも有効な対策の1つです。
暦年課税を適用すると年間110万円まで非課税で贈与を行うことができます。
この非課税枠をうまく活用して贈与を行い、所持している財産総額を減らすことで、相続の際に発生する相続税を抑えることにつながります。
しかし、1年間の贈与額が基礎控除である110万円を超える場合は贈与税がかかりますので、生前贈与を行う場合には贈与税負担と相続税負担の両方を比較検討してから行う必要があるでしょう。
また、住宅資金、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与など、それぞれの条件を満たす場合にのみ、一定額の贈与税が非課税となる制度もあります。これらは暦年課税と併用することができるので、合わせて活用することもおすすめします。
3.贈与税の課税対象・非課税対象となるケース
実際に、形のある財産がある人から別の人に、合意のもと無償で移転されれば、贈与があったとすぐにわかります。
しかし、中には贈与があったのかどうかわかりにくいものもあるのではないでしょうか。
贈与にあたる行為だと知らずに行ってしまい、あとで思わぬ税負担が生じることがないように正しく課税対象となる行為を理解しておくことが大切です。
3-1.贈与税の課税対象となる場合
まず、贈与税の課税対象となる場合です。
対価の受け渡しがなく無償で名義変更が行われた場合や、契約者と受取人が異なる保険契約による死亡保険金を受け取った場合、借金の返済を肩代わりしてもらった場合などは贈与があったとみなされ、贈与税が課されます。
3-2.贈与税の非課税対象となる場合
一方、贈与があっても非課税とされる場合もあります。
例えば、家族などの扶養義務者間での生活費や教育費の贈与や、個人から受ける香典・花輪代・年末年始の贈答そして祝物または見舞いなどの金品で常識的な範囲のものなどは非課税になります。
また、法人からの贈与を受けた場合は、所得税が課税されるため、贈与税はありません。
4.まとめ
相続税対策として賢く生前贈与対策を行う場合には、贈与税の課税方法の仕組みをよく理解することによって、税負担を考慮しながら決めることが大切ではないでしょうか。
暦年課税を選択すると、年間110万円までは非課税で贈与を行うことができるため、少額の贈与の場合や長い時間をかけて、こつこつと贈与を行いたい方には向いている課税方法だといえるでしょう。
しかし、一度に基礎控除額を超える多額の財産を贈与したい場合などには、上述した特例やもう1つの課税方法である相続時精算課税制度を選択したほうがいい場合もあります。
その際には贈与の方法について、一度、専門家に相談をしてみるといいでしょう。