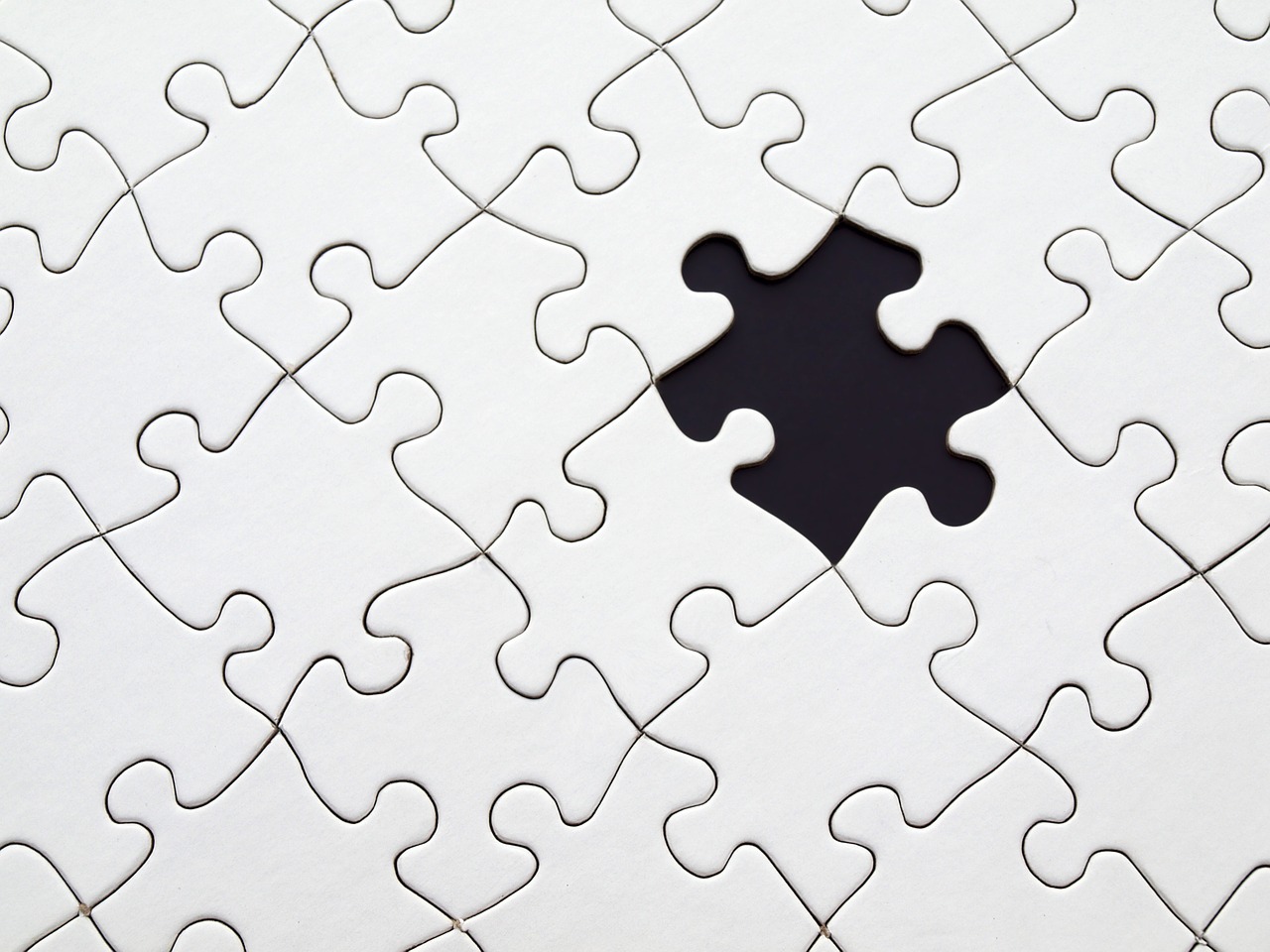相続税が改正され、富裕層以外の一般家庭でも相続税がかかると言われるようになりました。
それならば住宅を生前に贈与してしまえば、相続税がかからずに済むのではないか?と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確かに、住宅が相続財産の多くを占めているというケースは多いですから、生前贈与を上手く行えば大幅に相続税を減額できる可能性はあります。
ただし、生前に住宅を贈与した場合には、通常贈与税がかかります。
また、相続の場合には、被相続人と同居していた親族が多額の相続税の納税資金の工面のために住宅を売却しなければならない…という事態を回避するための大幅な財産評価減の特例があります。
同様に、生前に贈与を行う場合にもいくつかの特例があります。
これらを踏まえた上で、どのような場合に生前贈与をした方が良いのか、あるいはどのような場合に相続まで待った方が良いのか、その判断をしていきましょう。
1.生前贈与とは
生前贈与とは、自分(贈与者)の財産を無償で相手(受贈者)に与えることです。
通常の贈与は、贈与税がかかります。その非課税枠は110万円ですので、住宅の生前贈与は、これを大きく上回ることが想定されます。税金のことを考えれば、通常、相続まで待った方が税金を抑えられるのですが、実は配偶者や子・孫への住宅の生前贈与に関する特例が存在します。
そこで、各種の特例をうまく適用させ、相続財産を上手に渡していく方法を見ていきましょう。
1.配偶者への生前贈与
1-1. 贈与税の配偶者控除とは
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、住宅または住宅取得のための資金贈与を行った場合に、その贈与金額から2,000万円が控除される制度です。通称『おしどり贈与』と言われています。
また、贈与税には1年当たり110万円の基礎控除がありますので、合計して2,110万円までの控除が受けられます。
贈与額が2,110万円を超える場合には、超えた部分に対して通常の贈与税が課税されます。
長年連れ添ってきたご夫婦はぜひ検討・活用してみたい制度です。
1-2.適用要件
おしどり贈与を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
- 夫婦の婚姻期間が(入籍後)20年以上であること(内縁関係の期間は除く)
- 受贈者の居住用不動産の現物、または居住用不動産を取得するための資金の贈与であること(住宅とは通常居住用建物及びその土地のことを指しますが、この特例では土地だけの贈与でも対象となります。現在夫婦で居住している家の土地のみを妻のものにするという方法も可能です。)
- 受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日まで贈与により取得した不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
- 受贈者が、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行っていること
- 取得する居住用不動産の面積や築年数等に関する要件はない
1-3.注意点
おしどり贈与を受けるに当たり、以下の点に注意しましょう。
- おしどり贈与は、同一の配偶者間では一生に一度しか適用されません。
- 居住以外の用途(賃貸等)の不動産を贈与したり、贈与された金銭を他の目的で使ってしまった場合などには、おしどり贈与が適用されません。
- 居住用不動産を現物で贈与する場合には、日本国内にあるもの(その敷地が借地権の場合も含む)のみに限られます。
- 店舗兼用の住宅の場合には、居住用部分のみが適用となります。ただし、居住用部分がおよそ90%以上であれば「すべてが居住用」とみなされます。
- 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合、通常はその贈与財産も相続税の課税価格に加算することとなりますが、おしどり贈与が適用された財産については、相続開始前3年以内の贈与であっても相続財産に加える必要がありません。また、贈与されたのと同じ年に贈与者が亡くなったとしても、おしどり贈与は適用できることになっています。
- おしどり贈与により贈与税が全くかからなかった場合でも、不動産取得税や登録免許税は課税されます。また、金銭の贈与を受けて居住用不動産を取得した際の購入諸費用なども通常通り必要となります。
2.子や孫への生前贈与
2-1.住宅取得のための資金贈与の特例とは
贈与者が直系卑属(子・孫)へ住宅取得資金として贈与を行った場合に、一定の金額が非課税(平成27年度中の契約締結で最高1,500万円)となる制度です。
非課税枠は贈与を行う時期や住宅の条件により異なります。

この制度は単独で使うこともできますし、次の章で述べる「相続時精算課税制度」と組み合わせて使うことも可能です。
2-2.適用要件
住宅取得資金贈与の特例を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
- 住宅の取得のために金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てていること
- 受贈者が、贈与を行う年の1月1日において20歳以上であること
- 受贈者が、贈与を受けた翌年3月15日までに住宅を取得し居住を開始していること、または3月15日の時点で未完成・未入居となる場合でも完成後遅滞なく居住することが確実であること
- 建物の登記簿面積が50m2以上240m2以下であること(震災被災者は除く)
- 中古住宅の場合、建物の築年数が、マンション等耐火建築物の場合は25年、木造等耐火建築物以外の場合は20年以内であること
※ただし、この年数を超える場合でも、以下の要件を満たしていれば適用可能です。
(ア)新耐震基準に適合していることについて証明されたもの
(イ)既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のもの
(ウ)新耐震基準に適合しない物件であっても、取得日までに耐震改修工事の申請等を行い、居住日までに耐震修正工事を完了している等の要件を満たすもの
- 受贈者の贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下であること
- 受贈者が、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行っていること
2-3.注意点
住宅取得資金贈与の特例を受けるに当たり、以下の点に注意しましょう。
- 居住用不動産そのものや、住宅ローン返済資金の援助など、住宅取得後に贈与された金銭は適用外となります。
- 原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、その住宅に居住することが条件です。
しかし、様々な事情で計画から完成して居住するまで予定通りのスケジュールで進まないこともよくあります。
請負契約により住宅用家屋の新築をする場合には、その贈与を受けた年の翌年3月15日現在において未完成・未入居であっても、その家屋がいわゆる「棟上げ」を了した以降の状態にあれば「新築」とみなされ、完成後遅滞なく居住する旨を届け出れば特例が適用されます。「棟上げ」を了していることについては建築業者からの証明が必要となります。ただしこの場合でも、その贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住していなければ適用は取り消されます。
売買契約により建売住宅や分譲マンションを購入する場合には、売買契約を締結しただけでは「取得」には当たらず、贈与された年の翌年3月15日までに完成引き渡しを受けなければなりませんので間違えないようにしてください。