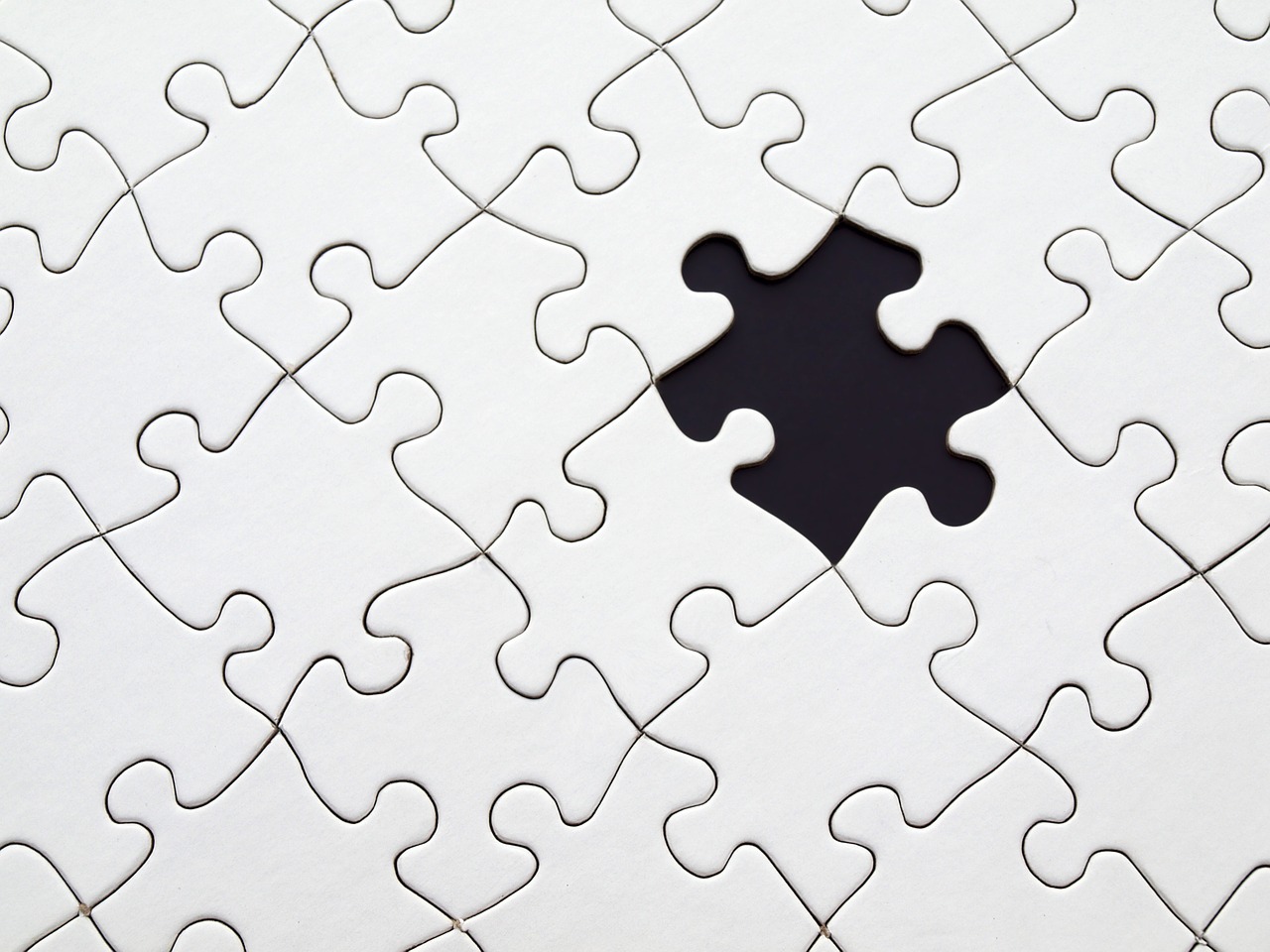・社会的な判断はできる
・社会的な判断が難しい
・問題を解決することができない
・複雑な家事はできない
・しばしば失禁がみられる
3-3. 作成する遺言の種類
認知症の人が遺言書を作成する場合は、公正証書遺言がおすすめです。
自筆証書遺言はその人本人が書いたという証明が難しく、また本人の意思によって書いたものであることも証明しにくいので、あまりおすすめではありません。有効か無効かは、最終的には裁判所の判断となりますが、公証人も後に無効となる遺言書を作成することはできませんので、遺言者の状況をしっかりと観察し判断してくれます。
また、公正証書遺言は裁判でも無効となりにくい信頼性がありますので、認知症であるなど、その疑いがある場合はまずは公正証書遺言を検討しましょう。
3-4. 医師の診断
遺言書を作成する時、医師の診断書を添付すると良い場合があります。周りから認知症だと思われているが、本当はそうではないことの証明のためや、軽度であることの証明のためです。この証明は直ちに遺言書の有効を証明するものではありませんが、裁判で争われた時に証拠となります。そのため、自身に不利となる診断書はあえて添付する必要はありません。
ちなみに、診断は「認知症であるかないか」の診断であって、「遺言書が書けるか書けないか」の診断ではありません。前者は医学的診断なので医師が判断することができますが、後者は法務的な判断になるため、医師が判断することはできませんので注意しましょう。
4. 意思能力があるかどうかの基準
意思能力があるかは目に見えないため、判断が非常に難しく、一概にこうとは言えません。ここでは裁判で意思能力がないとされ、遺言書が無効になった裁判例を紹介します。
4-1. 頷くことしかできない人の遺言は無効
(最高裁 昭和51年1月16日判決)
肝臓障害で入院したAさんは、弟であるBさんに対して、内縁の妻との子どもであるYを認知する旨の公正証書遺言を作成したいと伝えました。
Bさんはすぐに公正役場に行き、Aさんの遺言内容を伝え、公証人が遺言の原案を作成しました。
その後、公証人が原案を持ってAさんのもとに行き、「子どものことで遺言するのは本当か」「Yを子どもとして認める公正証書遺言を作ってよいか」と聞きましたが、それに対してAさんは頷いただけで一言も言葉を発しませんでした。
当時、Aさんは切迫昏睡状態にあり、判断力はひどく低下していたため、その応答には信用が置ける状態ではなかったのです。
その後、Aさんは亡くなり、他の相続人により認知無効の訴えが起こされ、それが認められたため、遺言書は無効となりました。
4-2. 各人の供述が整合しておらず無効
(東京地裁 平成18年7月4日判決)
Aさんは公正証書遺言を作成しましたが、作成当時は重度の認知症で、単純な内容の遺言ですら理解できないほどでした。
それにも関わらず公証人は公正証書遺言を作成してしまい、さらに遺言作成時の相続人の供述や証人の供述が、当時の介護記録の生活状況と整合していなかったため、遺言能力がないとみなされ無効になりました。
4-3. 認知症であるにも関わらず、遺言内容が複雑なので無効
(横浜地裁 平成18年9月15日判決)
Aさんは知能機能検査で重度の認知症だと診断をされ、子供の数や病歴などの長期的な記憶についても記憶障害がありました。
また、会話についても話しかければ応答はあるが、簡単な会話のみに応答するのみでした。
それに対してAさんが作成した遺言内容は、多数の不動産等を複数の相続人に相続させ、また一部を共有にしたり、遺言執行者を分けて指定するなど、かなり複雑なものでした。
ここまで重度の認知症の人が、こんなに複雑な遺言内容を理解し遺すのは不可能であると判断され、無効となりました。
4-4. 遺言者が生前大切にしていた財産への配慮が無く無効
(大阪高裁 平成19年4月26日判決)
Aさんは認知症で、度重なる不穏行動などから投薬を受けていました。
遺言作成当日は酸素吸入をしており、その一週間後には危篤状態になり、まもなく亡くなりました。
遺言内容は文案から変更されていましたが、これがAさんの指示であったかは定かではなく、またAさんが生前大切にしていた財産への配慮が全くありませんでした。